花京院がその馬を見つけたのは、二つの人工太陽がちょうど両方とも沈んでいるときだった。
浮遊車のライトに照らされた馬を見て、彼はとても驚いた。
まだ野生の馬が生きているなんて、考えたこともなかったからだ。
彼は自分の星に馬を連れ帰ろうと申請を出したが、当然ながら許可は下りなかった。
しかし花京院は模範的なエージェントだったから、その馬の所有権は認められた。
彼は三日間もデータベースと相談して、黒くたくましい馬を承太郎と名付けた。
そして、
「君の名は今日から承太郎だ。僕は君の所有者になった花京院という。よろしくね」
と声をかけた。
そこで初めてその馬は、緑の瞳をきらめかせて、
「ああ、よろしくな」
と言った。
花京院の知りうる限り、地球産の生物で第3高等言語を扱えるものは一種しかいない。
そしてそれはヒト科であり、ウマ科ではなかったはずだ。
だが彼はこの美しい馬にすっかり心を奪われていたので、承太郎が口を利くことはあまり気には留めず、すぐに彼らは仲良くなった。
花京院は自分の居住スペースの一角に、承太郎のためのコーナーを作った。
彼はそこを花で飾り立て、心地よい音楽をかけ、食事は必ずそこで、承太郎とともに取るようになった。
承太郎は無口な方だったが、花京院が疑問に思う事柄のおおよその答えを知っていた。
承太郎は花京院に、全てを呑み込む巨大な狼の話をしてくれた。
世界の海を取り巻く大蛇の話を、冥府を統べる女神の話をしてくれた。
花京院はすっかり承太郎の話に引き込まれて、仕事の時間以外を彼のそばで過ごすようになった。
沈黙のときにも、二人でいるのは気持ちのいいことだった――たとえ意識が闇に包まれる睡眠時でさえ。
そしてとうとうその日がやってきた。
花京院は承太郎の鼻先にキスをすると、8つの瞳いっぱいに悲しみを湛えてこう言った。
「承太郎、僕はもう来たところに帰らなくちゃならない。この星での任務期間が過ぎてしまったんだ。君はこの星の生まれだから、僕の星へ連れて帰ることはできない。……お別れだ」
「もっと長いこと、ここにいることはできないのか?」
「衛生上の問題でね。あんまり長いことここにいると、この星と同調してしまう。ヒト科の生物が絶滅した理由を知っているだろう」
「ああ、戦争だ」
「争いの波長は、僕らにとって刺激が強すぎる。『血がはやる』とか、『敵を討ち滅ぼす』とか、そういうのに向いてないんだ。君は得意そうだけど」
「……俺は、元々軍馬だった。主人が死んだので独りになっただけだ。俺は勝利をもたらすものだった」
「だったらやっぱり、僕の星には連れて行けないな。あそこでは安寧が君を殺すだろう」
それから二人は黙って見つめあった。花京院には8つの黒い目があった。
緑色でスジのある長い四肢があった。
彼のたゆたう触角は、片目を隠すほど立派なものだった。
承太郎には黒く艶やかな毛があった。
緑に輝く瞳があった。
力強くたくましい、8つの足があった。
こんなに違うのに、二人は奇妙なほど似通っていた。
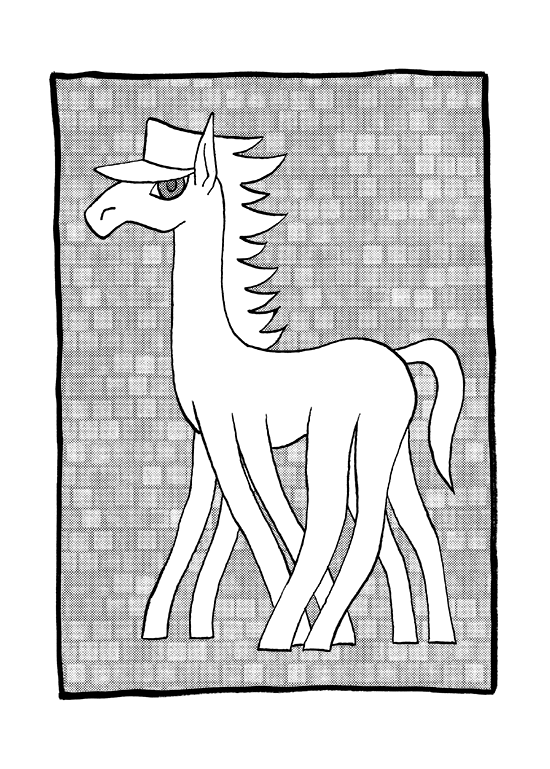
「五千年待った。とうとう会えたのに、別れるわけにはいかねえ」
と承太郎が言った。
「そうだね、いつだって君は僕を見つけ出してくれたけど、今回は特に長かったから」
神話の時代から宇宙の時代まで。
やっとやっと巡り会えたのだ。
「もし、」
と花京院が言った。
「この星ほど好戦的ではなくて、僕の星ほどおっとりもしていない星のありかを僕が知っていると言ったら?」
「もし、」
と承太郎が言った。
「俺の足が星々の間を駆けられると言ったら?」
そうして彼らは手を取り合い、神話の外、他に誰もいない世界へ、自分たちだけの物語を紡ぎに出かけていった。
